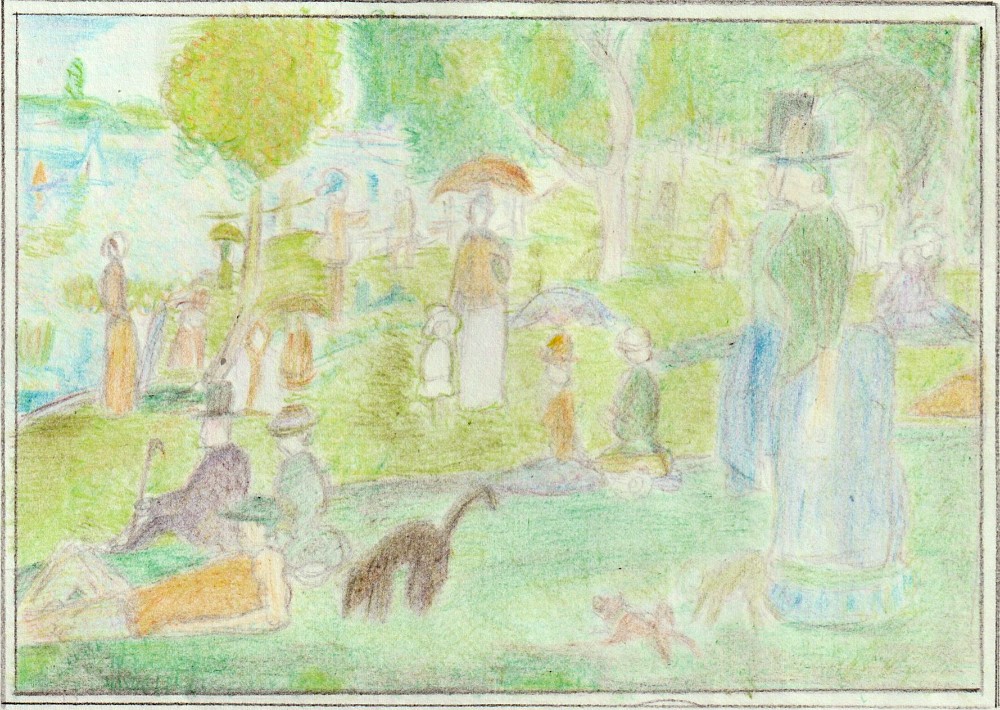舞台
フランス

フランス美術は西洋絵画史の主要舞台の座を確立しました。イギリス風景画の伝統もスペイン画家ゴヤの系譜もフランスに吸収され、オランダ画家ゴッホもこの地での修行を得て覚醒しました。
背景
印象派展の開催

1874年、モネ・ルノワール・セザンヌ・ドガ・ピサロらによって、展覧会が開かれました。

彼らの作品に共通して見られる「スケッチ的な作風」から、この展覧会に集まった彼らは総称して、「印象派」と命名されることになります。
多様性に満ちた印象派グループ

しかし実際のところ、彼らには明確な意味での共有された美学上の理念はなく、それぞれ「個性的な探求」へと歩を進めました。
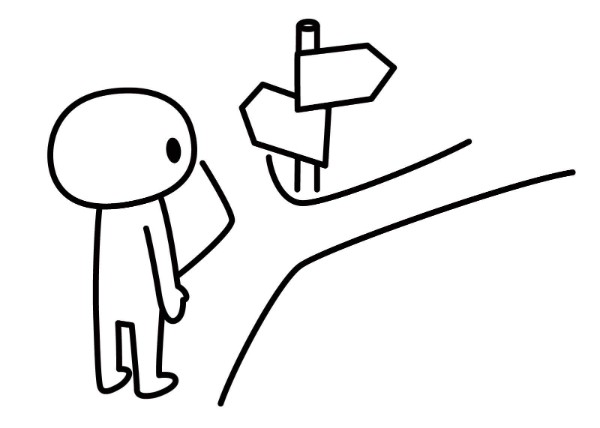
そのため、具体的に誰を印象派に含めるかについては意見の分かれるところです。

ただ、このように多様性があったからこそ、印象派は広く展開することが出来たのは間違いありません。
特徴と背景
新しい表現の追求

クールベやマネによって、現代生活を題材にした絵画の道が切り開かれた今、それを実際にどう表現して行くかという問題が、次の世代に託されることになります。
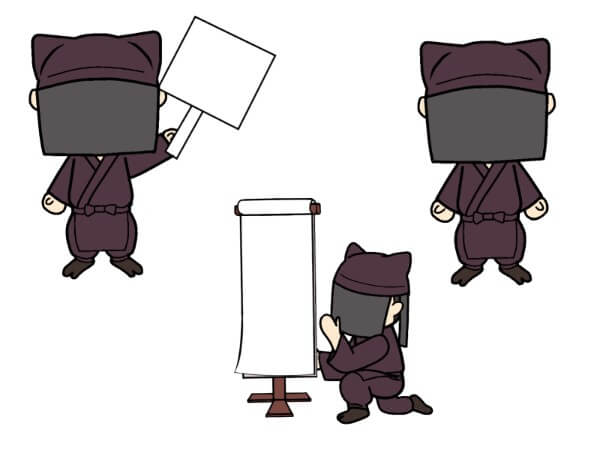
これまでの絵画では、「色彩」や「光」というのはあくまでも主題を演出するための道具に過ぎず、それ以上でもそれ以下でもありませんでした。
色彩・光を主題にする

しかし印象派は、「色彩」と「光」それ自体を主題として扱ったところに画期性があります。
「筆触分割」・「視覚混合」

その意味で、もっとも印象派と呼ばれるに相応しい画家は、モネです。彼は「筆触分割」・「視覚混合」という二つの手法を駆使して、より自然の光に近い効果を狙いました。

パレット上で色を混ぜるのではなく、紙上に直接色を並べ、それを離れて見ることによって色が混ざったように見えるという、視覚の作用を利用したのです。

またこの手法は、科学的な色彩理論に裏付けを得たものでもありました。
分析的なマネ
クロード・モネ|1840−1926|フランス

モネは様々な風景を観察しながら、網膜に残された色を分析して作品に仕上げます。光の印象を再現するためにも、彼はくっきりとした輪郭を用いず、感覚主義の局地へと突き進みました。
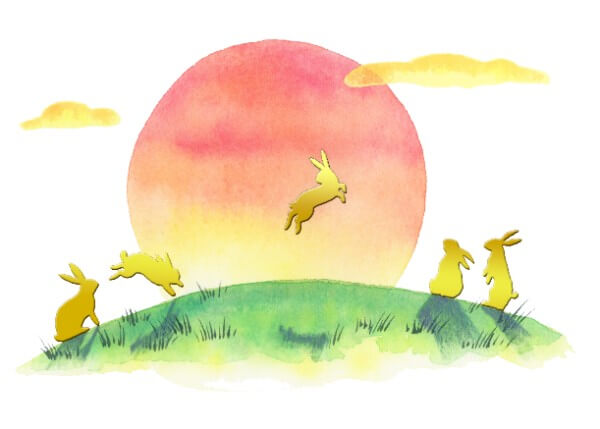
そして睡蓮の連作に代表される、刻々と変わり行く光の効果へとたどり着いたのです。

印象派を象徴する画家として、もう一人挙げるべき人物は、ルノワールです。彼もまた、自らの作品に「視覚混合」を用いました。
楽観的なルノワール

しかしルノワールの場合、モネほど分析的ではなく、むしろ楽しい雰囲気を演出するために活用されています。
オーギュスト・ルノワール|1841−1919|フランス
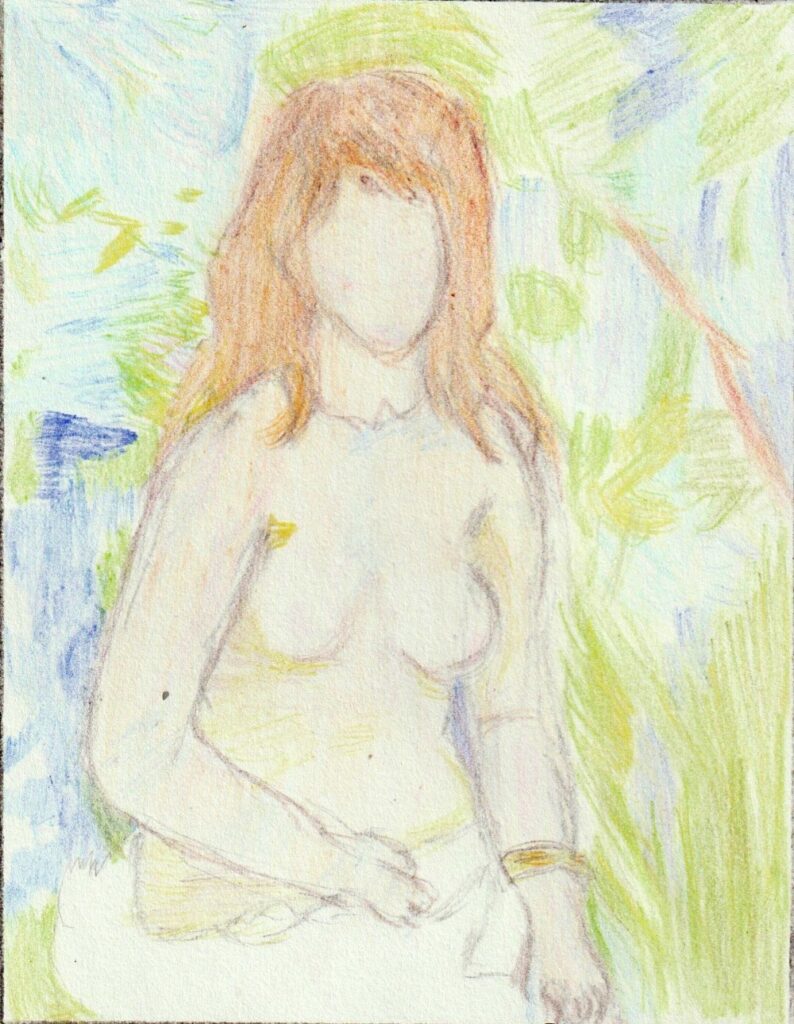
ルノワールは風景よりも人物に関心を寄せました。どういうわけか男性を描くのは苦手で、子供や女性にのみ才能を発揮します。
内部分裂を起こす印象派

印象派は追従者を生む一方で、当然多くの反感も買いました。しかも敵は外部だけではなく、むしろ初めから内部分裂さえ起こしていました。この多様性もまた、印象派の特徴です。
アングルを尊敬するドガ
その一人として、「エドガー・ドガ」が挙げられます。ドガは印象派展に参加しているという理由から、基本的には印象派に分類されますが、その作風は大きく異なり、彼の「知的な構図」や「デッサン力」などは、むしろアングルを筆頭に、ルネサンス的な古典に由来します。
ありのままではなく、計算的な構図
エドガー・ドガ|1834−1917|フランス

ドガは現代生活の様相を深く研究し、様々な階層に生きる人々を客観的な視点で観察する一方で、実際に描かれる作品では、観察から自ずと生まれてきたかに見える外観に反し、極めて意識的に計算されたものでした。
参考文献
美術史〈西洋〉|編・中山公男 中森義宗|近藤出版社
西洋美術史|監修・高階秀爾|美術出版社
西洋絵画史入門史|著・諸川春樹|美術出版社